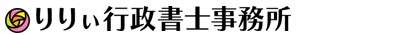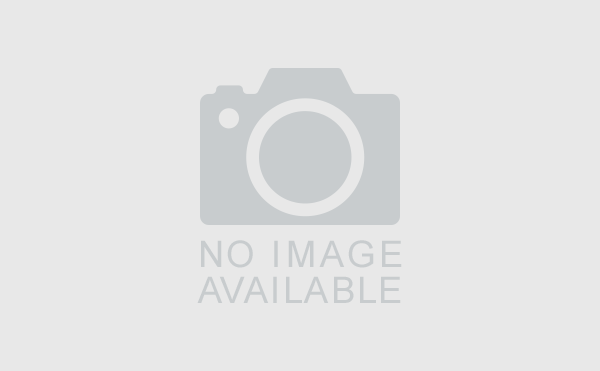永住者の配偶者ビザから永住ビザ申請への条件と手続きのポイント
永住者の配偶者等の在留資格の方や、この在留資格に該当する方で、永住者へ変更したい方の条件や申請に必要な書類などを解説いたします。
愛知県名古屋市でビザ申請・永住・帰化申請サポートをしているりりぃ行政書士事務所です。ご相談予約はこちらから受け付けております。どうぞご利用ください。
永住者の配偶者等と永住者の違い
2点の主な違い
在留資格『永住者の配偶者等』をお持ちの方と、『永住者』の主な違いは、次の2点です。
在留期限
【永住者の配偶者等】
永住者の配偶者等の方は、在留期間があり、期限ごとに更新申請が必要です。
【永住者】
永住者は無期限に日本に住むことができます。
不安定な立場
【永住者の配偶者等】
永住者の配偶者等は、もし配偶者の方と離婚したり、死別した場合、入管に届出なければなりません。
そして、日本に引き続き在留を希望する場合は、ビザの変更をすることになります。
このときに『定住者』ビザへ変更する方が多いですが、日常生活を送れる日本語能力があること、生活をしていく資産や技能があることが必要です。
もし、他にも該当するビザがなければ帰国することになります。
このように、配偶者との関係により、突然不利な立場になることがあり得ます。
【永住者】
永住者は、相手方と離婚、死別があっても、自分が永住者であるので安定して日本に住むことができます。
在留資格が永住者の配偶者等ではない場合
在留資格が『永住者の配偶者等』でなくても同じ条件で申請できます
現在おもちの在留資格が『永住者の配偶者等』でなくても、この在留資格に該当する方は、今の在留資格のままで、同じ条件で永住申請ができます。通常の永住申請よりも緩和される条件が多いです。
具体的には、次の方が該当します。
- 永住者の配偶者
- 特別永住者の配偶者
- 日本で生まれた永住者・特別永住者の子供で引き続き日本に在留している者
(※子供は実子・嫡出子・認知された非嫡出子 養子は該当しない)
永住者申請に必要な期間
通常の永住申請よりも短い期間で申請できる
通常、永住申請ができるのは10年以上引き続き日本に在留した者で、定住者でも5年以上在留が条件です。しかし、永住者の配偶者等をおもちの方はこの期間が短くなります。
具体的には次のとおりです。
実体がある婚姻生活が3年以上継続
+
引き続き1年以上日本に在留
子どもの場合は1年以上日本に継続して在留
永住者の配偶者から永住申請の条件
永住者になるための法律上の要件
永住者になるための法律上の要件は次のとおりです。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていない
- 納税・ねんきん・健康保険の保険料の納付をしている
- 入管法に定める届出などの義務を適正にしている
- 在留期間「3年」以上をもって在留している
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない
永住者の配偶者等から永住者へ変更したい場合は、他の在留資格から永住者になるよりも必要な要件が少なくなります。
①の罰金や懲役刑などは、受けている方は少ないと思います。
⑤の公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないとは、感染症にかかっていない、慢性的な薬物中毒者でないことです。
一般的に引っかかるのは、②➂④です。こちらについて詳しくみていきます。
納税・ねんきん・健康保険の保険料の納付をしている
特に大切なのは、税金を納める必要がある場合に、きちんと納めていることです。
住民税を納めるべき人は払っている必要があります。会社の給料から引かれている人は良いですが、自分で納付するようにしている方は、確認が必要です。
また、年金や健康保険料も、会社から引かれている方は心配ありません。そうでない方は国民ねんきんや国民健康保険に加入義務があります。これもきちんと支払っているかをみられます。
また、国民年金や国民健康保険を支払っている方は、証明として、納付書や領収証書を残しておくことが大切です。
また、事業主の場合は社会保険の適用事業所の場合、本人自身に加え、事業所における年金、保険料の納付もきちんとされているかが大切になってきます。
入管法に定める届出などの義務を適正にしている
具体的には次の届出をきちんと行っていることです。
- 引っ越しなどで住所が変わったときは市区町村役場へ
- 氏名、生年月日、性別、国籍が変わったときは入管へ
- 配偶者と死別、離婚したときは入管へ
それぞれ14日以内に届出する必要があります。
在留期間「3年」以上をもって在留している
現在もっている在留カードの在留期間が、『3年』『5年』の方は永住申請ができます。他の条件がそろっていても、在留期間が『1年』の方は申請できません。更新申請をしたときに、3年の許可が出てからになります。
永住申請に必要な期間で説明した通りの期間に加え、在留カードに記載の在留期間が3年、5年の方が申請可能な条件に該当します。
実体がある婚姻生活が3年以上継続
+
引き続き1年以上日本に在留
子どもの場合は1年以上日本に継続して在留
在留カードに記載の在留期間
『3年』『5年』
永住申請に必要な書類
永住者の配偶者から永住者の必要書類
- 永住許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm) ※16歳未満は不要
- 申請人の方が永住者の配偶者である場合次の(a)(b)のどちらか
(a)配偶者との婚姻証明書
(b)申請人と配偶者の方との婚姻関係を証明する(a)に準ずる文書 - 申請人の方が永住者・特別永住者の子どもである場合次の(a)(b)のどちらか
(a)出生証明書
(b)申請人と永住者・特別永住者との親子関係を証明する(a)に準ずる文書 - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 (※マイナンバー省略・他は省略なし)
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明できる(a)~(c)のいずれかの資料
(a)会社等に勤務している場合 在職証明書
(b)自営業等である場合 確定申告書控えの写し 営業許可書の写し(ある場合)
(c)その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※申請人・配偶者のお二方とも無職の場合も、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出 - 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)※永住者・特別永住者の実子等は直近1年分
- 直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方
直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)※永住者・特別永住者の実子等は直近1年分 - 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)※対象期間の指定は不要
- 預貯金通帳の写し(取引履歴が分かるweb通帳の画面の写しも可※Excelファイルなど加工できるものはNG)
- 他に所得を証明できるもの
- 申請人及び申請人を扶養する方の①ねんきん及び②健康保険の保険料の納付状況を証明する資料
※基礎年金番号や保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りするなど、復元できない状態にして提出
①直近2年間(永住者・特別永住者の実子等の場合は直近1年間)の年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 直近2年間で厚生年金などに加入している方
(a)(b)どちらか
(a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
(b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 - 直近2年間で厚生年金+国民年金加入の方
(a)(b)どちらか+(c)
(a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
(b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
(c)国民年金保険料領収証書のコピー - 直近2年間すべて国民年金加入の方
国民年金保険料領収証書のコピー
提出することが困難な場合は、理由書+ねんきん定期便又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面を提出
②直近2年間(永住者・特別永住者の実子等の場合は直近1年間)の健康保険料の納付状況を証明する資料
- 現在、国民健康保険以外の健康保険に加入
健康保険被保険者証のコピー - 現在国民健康保険に加入中の方
国民健康保険被保険者証のコピー - 直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方
国民健康保険料(税)納付証明書
国民健康保険料(税)領収証書のコピー(提出が困難な方は、理由書を提出)
- 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合(a)または(b)を提出
(a)健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー(※直近2年間のうち事業主である期間)
(b)社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合) - 親族一覧表(永住者・特別永住者の配偶者の場合)
- パスポート又は在留資格証明書(提示)
- 在留カード(提示)
- 資格外活動許可書(提示) ※許可書を交付されている場合
- 身元保証書※通常は配偶者の方(永住者・特別永住者)が身元保証人になります
- 身元保証人の身分を証明できる書類(運転免許証コピーなど)
- 了解書
お問い合わせ

初回相談無料(1時間)
初回1時間ほど無料
(ご依頼頂いた方は相談料はかかりません)
事前にご予約頂いた方を優先的にご案内させていただきます。申請取次行政書士がご相談に対応いたします。
contact
お問い合わせ
受付時間:9:00~19:00
(土日祝 対応可能)
24時間受付
(1営業日以内にご連絡いたします)