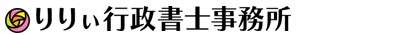愛知県名古屋市で永住者(永住権)申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
愛知・岐阜・三重
永住ビザ申請サポート
✔永住申請をしたい
✔永住か帰化か迷っている
✔家族も一緒に永住申請をしたい
✔今はまだだが、将来的に永住申請をする予定だ
丁寧なヒアリングにより、一人一人の状況に応じて申請をいたします。
目次
1.永住とは
2.永住者になると・・メリット
3.永住と帰化の違い
3.1 帰化
3.2 永住
4.永住許可には条件があります
4.1 素行善良要件
4.2 独立生計要件
4.3 国益要件
4.4 原則10年在留の特例
5.なぜ許可率が低いの?
6.永住申請の身元保証人とは?
7.contact
8.料金
永住とは
永住(えいじゅう)とは、わかりやすくいうと、自分の国籍のままで日本にずっと住むことができる権利です。
永住ビザの有効期限は、無期限となります。
入国時に初めから「永住権」をとることはできませんが、日本に数年在留してから申請ができます。そこで許可がおりると、永住者となります。

永住者になると・・メリット
永住者になるメリットは、次のようになります。
活動の制限がなくなります
今までは在留資格の範囲の中での職種・活動に限られましたが、この制限がなくなります。特に就労の面で、転職や事業をしやすくなります。在留資格の変更をしなくても転職でき、全く違う職種を掛け持ちすることもでき、仕事の面で自由度が増します。家族滞在の資格で、資格外活動許可をとっていた方も、永住が許可されると就労制限がなくなります。
在留期間がなくなります
今までのように、何年かごとの在留資格(VISA)の変更、更新申請に時間と手間をとられることがなくなります。在留カードの更新のみとなります。永住者になっても、入国管理局でのカードの更新は忘れないようにしなければなりません。永住者のカード更新についてはこちらをクリック
社会的信用度が増します
住宅ローンや、事業資金を借りる際に有利になります。
家族も永住許可をとりやすくなります
家族同時申請も可能です。一緒に申請することが難しい時でも、申請者本人が永住許可をとると、配偶者や子供は「永住者の配偶者等」や「定住者」など、就労制限のない在留資格が取得できます。
永住と帰化の違い
永住と帰化の違いは、以下のようになります。
| 永住 | 帰化 | |
|---|---|---|
| 国籍 | 自分の外国籍 | 日本国籍 |
| 在留資格の変更・更新 | 必要なし | 必要なし |
| 在留カード | あり 7年ごとのカード更新が必要 | カードなし |
| 再入国許可 | 期限あり | 必要なし |
| 選挙権 | なし | あり |
| 退去強制(強制的に国外へ退去) | あり | なし |
帰化
国籍
帰化は、日本国籍を取得することになりますので、日本人と同様の権利が与えられます。
在留期間を気にする必要がなくなります
ビザの変更・更新が不要になります。また、永住では在留カードを持つことになりますが、帰化をすると在留カードを返納するので、カードの更新も必要ありません。
日本のパスポートを取得できます
みなし再入国の期間を気にすることはなくなります。再入国許可をとる必要もなくなります。
公務員になることができます
日本国籍が必要な公務員になることが可能になります。
選挙権、被選挙権が与えられます
選挙で投票することができます。また、立候補することもできます。
永住
国籍
今の外国籍のままです。
再入国の期限
永住者は再入国許可申請をする対象です。もっとも、みなし再入国に該当する方は入管での事前許可申請は必要ありません。
みなし再入国許可:出国の日から1年間
再入国許可:最長で5年間有効の期限を守る必要があります。
選挙権
永住者は選挙権はありません。
退去強制の対象
永住者も在留資格の取り消しの対象であります。
退去強制の事由に該当すれば、国外退去を強制されることもあるので、永住許可後も問題のないように過ごすことが大切です。
帰化の方が良く見えますが、帰化して日本人になり、自分の国籍を放棄するということを、よく理解する必要があります。
日本は二重国籍を認めていません。母国へ帰るのにビザが必要になることもあります。国家間の不和や対立、伝染病などで母国に帰るのが難しくなることもあるかもしれません。
永住か、帰化かで迷っている方は特によく考えて申請をする必要があります。
永住許可には、条件があります
永住許可の条件は次の3つとなります。
①素行善良要件
②独立生計要件
③国益要件
この3つの要件は、具体的には次のようになります。
①素行善良要件
法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
②独立生計要件
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 生活保護を受給していないこと
- 将来にわたって自活し、安定的な収入が続くことが可能である
- 本人に収入がなくても、世帯単位で収入、預貯金、不動産等の資産がある方は該当します
1人で申請するならば、おおよそ年収が300万ほどは必要な傾向にあります。また、扶養家族の人数が増えるとその分、生活していける収入が必要となってきます。
③国益要件
- 引き続き10年以上日本に在留していること。10年間のうち、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」は除く)又は居住資格をもって5年以上日本に在留していること
※特例あり・後ほど説明があります
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
- 現在、在留期間「3年」以上をもって在留している
現在お持ちの在留カードの在留期間が「3年」以上になっている必要があります。「1年」などの方は、更新時に3年になるまで待たなくてはなりません。
- 公的な義務である税金、年金・保険料の支払い、入管への届出などをきちんとしていること
住民税を払っている
ねんきん・健康保険料の納付をしていることが必要です。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことなど
感染症にかかっていないことや、慢性的な薬物中毒者でないことなどです。
※日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子である場合には、①②の要件に該当する必要はありません。また、難民の認定を受けている場合には、②に該当することを必要としていません。
原則10年在留の特例
次の方は、日本に10年在留していなくても、申請できます。
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留している方
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している方
- 「高度人材」の方は、ポイントにより1年以上又は3年以上在留、「特別高度人材」の方は、1年以上在留している方
引き続きとは?
永住申請に必要な在留期間で、『引き続き10年以上日本に在留』や、特例として継続して5年以上などがありますが、この『引き続き』とはどのような状態のことでしょうか?
これは、在留資格が途切れることなく日本に在留し続ける、という意味です。
日本で留学生として何年か滞在後、本国に帰り、5年後に日本で働き始めた人がいるとしましょう。この場合、一度在留資格が途切れているので、留学の期間は引き続き在留した年数に入りません。
また、再入国で1回の出国が3か月以上の方や、年間100日以上の出国がある方は要注意です。『引き続き』在留していないと判断される可能性が高いです。
出張など特別な理由がある方は、具体的な説明や真実であることの証明が必要となってきます。
永住申請の許可率・なぜ許可率が低いの?
近年永住申請の許可率は約50%~60%となっています。
多くの永住申請が不許可になっているということになります。
この低い許可率の中には、自分の判断で申請してしまい、書類に不備があった、在留年数が足りていなかった、などの方もいます。永住申請には条件がありますが、そもそもこの条件に当てはまっていない方も多いです。現在の在留資格によって、必要書類も違ってきます。
また、不許可後に自分で再申請をしてみたが、直すべきところを直さず、間違った方向にいってしまうこともあるでしょう。
当事務所では、まず永住申請ができる要件に当てはまるか、確認からしていきます。ご相談後、納得いただいてからの申請となります。どうぞご利用ください。
永住者の申請に必要な身元保証人とは?
永住者の申請には身元保証人が必要です。
永住者の申請をする際に必要な書類として、『身元保証書』があります。
これを1通、身元保証人に書いてもらうことになります。また、身元保証人の身分証明書として、運転免許証のコピーなども提出する必要があります。
永住者申請の身元保証人になることができるのは、次の3つのどれかに当てはまる人だけです。
①日本に住んでいる日本人
②永住者
➂特別永住者
このうちの誰かにお願いすると良いでしょう。日本人の配偶者や永住者の配偶者がいる方は、その配偶者になってもらうのが一般的です。
そうでない方は、友達や知り合い、会社の人などにお願いする必要があります。
身元保証人について誤解が多いのは、『連帯保証人』とは違うということです。
入管法での身元保証人の責任は。。
保証事項
滞在費や帰国費など経済的保証、法令の遵守などの生活指導
- 法務大臣に対して保証事項を約束
- 身元保証人に対する法的な強制力はない
- 保証事項を履行しない場合でも指導を受けるにとどまる
身元保証人として十分な責任が果たせない場合
それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠く
まとめると
法的な責任というより、道義的な責任を課すものであるといえる
身元保証人をお願いした時に断られる場合、これを説明する必要があります。連帯保証人と誤解している可能性があるからです。
contact

初回相談無料(1時間)
まずは、お問い合わせフォーム(24時間受付)または、お電話でご相談予約をよろしくお願い致します。こちらからご返信いたします。
・初回1時間程度 無料
・ご相談 ¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料はかかりません。事前にご予約頂いた方を優先的にご案内させていただきます。
あなたに代わって入管に申請いたします。在留カードの受け取りまでおまかせください。

申請取次行政書士
駒田美理 Misato Komada
申請取次行政書士とは
入管法などで定める一定の申請をしなければならない外国人に代わって、入管に申請書等の書類の提出などの手続きを行うことができる行政書士のことです。
原則としては本人が入管の窓口に行って申請しなければならないところが、申請取次行政書士に依頼すると、外国人の方が入管に行く必要がなくなります。
※入管の担当官が必要であると判断した場合、本人が入管窓口に行くことを求められる場合もあります。
flow
ご依頼までの流れ
- ①ご相談予約
- まずはお問い合わせフォーム又はお電話から、ご相談予約をお願い致します。こちらからご返信いたします。

- ②ご相談の日程・場所の調整
- 申請できる条件に該当するか、簡単にチェック致します。ご相談の日時や場所を決定し、予約確定となります。

- ➂無料相談(1時間ほど)
- 丁寧なヒアリングによりお客様に応じたお手続きをご提案の上、お見積りをご案内いたします。

- ④正式なご依頼
- 依頼されるかをご検討いただき、納得していただいた後に、正式なご依頼となります。

contact
お問い合わせ
受付時間:9:00~19:00
(土日祝 対応可能)
24時間受付
(1営業日以内にご連絡いたします)
料金
| 会社員 | ¥150,000~ |
| 経営者 事業主 | ¥180,000~ |
| 同居家族 1名追加 ※子供割引あり | ¥30,000~ |
出典 : 出入国在留管理庁ホームページ 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)