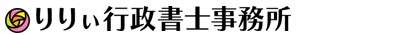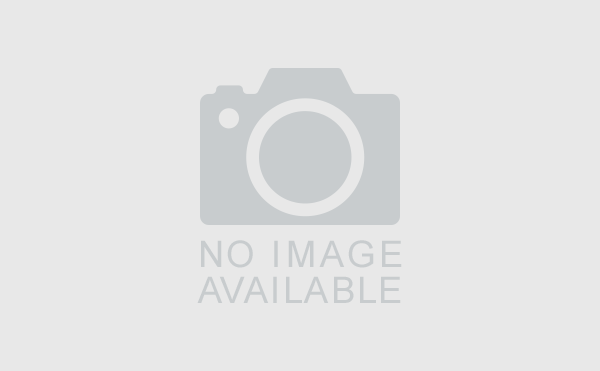就労ビザから永住者へ変更するときの条件や必要書類
就労ビザからの永住許可申請について、要件、必要書類をご説明いたします。
愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
『技術・人文知識・国際業務』『技能』『経営・管理』などの就労ビザから永住許可を受けるにはどうすれば良いのかについて、見ていきます。
『技術・人文知識・国際業務』からの永住申請については、こちらにも詳しくありますのでご覧ください。

就労ビザから永住者になるメリット
就労ビザから永住ビザになると、メリットが多い
活動の制限がなくなります
今までは就労ビザの在留資格の範囲の中での職種・活動に限られましたが、この制限がなくなります。就労ビザの範囲外の仕事ができます。在留資格の変更をしなくても転職でき、全く違う職種を掛け持ちすることもでき、仕事の面で自由度が増します。転職や離婚などがあっても、届出が不要になります。起業もできます。
ご家族が家族滞在で在留し、資格外活動許可をとっていた場合、永住が許可されると就労制限がなくなります。
在留期間がなくなります
今までのように、何年かごとの在留資格(VISA)の変更、更新申請に時間と手間をとられることがなくなります。永住者になると、在留カードの更新のみとなります。永住者になっても、入国管理局でのカードの更新はありますので、忘れないようにしなければなりません。永住者のカード更新についてはこちらをクリック
社会的信用度が増します
永住者になると、住宅ローンや事業資金を借りる際に有利になります。
仕事の面でも「永住者」というのは、安定して日本に住むことができるので、雇用側からしても安心感があり、雇用しやすくなります。
家族も永住許可をとりやすくなります
家族同時申請も可能です。一緒に申請することが望ましいですが、それが難しい時でも、申請者本人が永住許可をとると、配偶者や子供は「永住者の配偶者等」や「定住者」など、就労制限のない在留資格が取得できます。
就労ビザから永住者への要件とは
就労ビザから永住許可の要件
就労ビザから永住者申請する条件は、次の7つになります。ひとつずつ詳しくみていきます。
①素行が善良であること
法律を守り、日常生活でも住民として社会的に非難されることのない生活をしていること
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
具体的には、以下のようなことです。
・生活保護を受給していない
・将来にわたって自活し、安定的な収入が続くことが可能である
・本人に収入がなくても、世帯単位で収入、預貯金、不動産等の資産がある
ただし、扶養人数が多いと人数分の収入を求められますのでご注意ください。永住許可に必要な年収は、300万円+扶養家族一人につき70万円程度と考えておくと良いです。
※現在、預貯金がないからといって突然口座に大きな金額を入れることはやめた方が良いです。むしろ疑われることでしょう。
それよりも、安定継続して収入が入ることの方が大切になってきます。
➂原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
就労ビザの方が要件でつまずくところがこちらです。
原則として引き続き10年以上日本に在留している必要がありますが、その10年の中で、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」の期間は除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留している必要があります。
引き続きとは?
『引き続き10年以上日本に在留』や、『就労資格・居住資格をもって引き続き5年以上在留』とありますが、この『引き続き』とはどのような状態のことでしょうか?
これは、在留資格が途切れることなく日本に在留し続ける、という意味です。
日本で留学生として何年か滞在後、本国に帰り、3年後に日本で働き始めた人がいるとしましょう。この場合、一度在留資格が途切れているので、留学の期間は引き続き在留した年数に入りません。
また、再入国で1回の出国が3か月以上の方や、年間100日以上の出国がある方は要注意です。『引き続き』在留していないと判断される可能性が高いです。
出張など特別な理由がある方は、具体的な説明や真実であることの証明が必要となってきます。
10年の中で『就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留』とありますが、永住申請ではこの『5年以上』に「技能実習」「特定技能1号」だった期間は含まれません。
居住資格とは
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
であった期間が、5年以上あることです。
また、現在就労ビザの在留資格ではあるが、現実的に日本人の配偶者であったり、永住者の配偶者やその子どもである場合は、以下の特例に該当する可能性があります。
該当する方は、10年在留の要件が大幅に短くなります。
【特例】
就労ビザの方でも、日本人や永住者・特別永住者の配偶者やその子ども、高度専門職のポイント計算で高得点の者などは、特例として在留期間が短くても申請できます。
具体的には、次の4つの場合は、永住申請に必要な期間が短くなります。
日本人の配偶者・実子など
永住者、特別永住者の配偶者・実子など
これに該当する方は、
- 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留している
- その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留している
場合、許可申請の対象です。この場合、永住許可要件の①素行要件②生計要件は免除されます。
該当する方は、こちらに詳しく説明がありますのでご覧ください。
高度専門職のポイント計算をしたときに70点以上の者
3年以上継続して日本に在留している
+
永住許可申請日から3年前の時点を基準として、高度専門職ポイント計算を行った場合に70点以上の点数を持っていたことが認められること。
高度専門職のポイント計算をしたときに80点以上の者
1年以上継続して日本に在留している
+
永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に80点以上の点数を持っていたことが認められること。
【ポイント計算表】
- 技人国の方は、「高度専門職1号ロ」で計算します。技術・人文知識・国際業務の中の、「国際業務」に当たる方は高度専門職に該当しませんので、ご注意ください。
- 経営・管理で在留の方は、「高度専門職1号ハ」で計算します。
- 技能で在留の方は、高度専門職に該当する職種がありませんのでご注意ください。
出入国在留管理庁のHP(ポイント計算)
日本語 930001657.pdf (moj.go.jp)
English 001398882.pdf (moj.go.jp)
特別高度人材の基準を定める省令に規定する基準に該当する者
1年以上継続して日本に在留している者
+
永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材の基準に該当することが認められること
【特別高度人材の基準】
『高度専門職1号』の基準にすべて適合すること、また、以下のいずれかにも該当する方
1.高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導、教育をする活動(大学教授や研究者等)
2.高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学・人文科学に関連する知識又は技術を要する業務に従事する活動(企業で働く技術者・新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
1.2.のどちらかの方で、次のいずれかに該当する方
・修士号以上取得、年収2,000万円以上の者
・職歴10年以上、年収2,000万円以上の者
3.高度経営・管理活動
日本で事業の経営や管理に従事する活動(企業の経営者等)
3.に該当し、職歴5年以上であり、年収4,000万円以上の者
④罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
懲役、禁錮、罰金で処分されたり、少年法による保護処分が継続中でない者
そのようなことがあった方や、執行猶予期間が経過した方は、刑の消滅規定などにより申請できる場合もあります。
⑤公的義務を適正に履行していること
納税、年金・健康保険の保険料の納付、入管法の届出等の義務をしているかをチェックされます。
- 納税
税金を納める必要がある場合に、きちんと納めていることです。
住民税を納めるべき人は払っている必要があります。会社の給料から引かれている人は良いですが、自分で納付するようにしている方は、確認が必要です。 - ねんきん・健康保険の保険料の納付
会社の給料から引かれている方は心配ありません。そうでない方は国民ねんきん(20歳~60歳)や国民健康保険に加入義務があります。これもきちんと支払っているかをみられます。
また、国民年金や国民健康保険を支払っている方は、証明として、納付書や領収証書を残しておくことが大切です。
また、事業主の場合は社会保険の適用事業所の場合、本人自身に加え、事業所における年金、保険料の納付もきちんとされているかが大切になってきます。 - 入管法の届出の義務を行っているか
具体的には次の場合に、それぞれ14日以内に届出する義務があります。- 引っ越しなどで住所が変わったとき→市区町村役場へ届出
- 氏名、生年月日、性別、国籍が変わったとき→入管へ届出
- 所属機関に関する届出(所在地が変わったなど)→入管へ届出
⑥現に有している在留資格が「3年」「5年」であること
現在もっている在留カードの在留期間が、『3年』『5年』の方は永住申請ができます。他の条件がそろっていても、在留期間が『1年』の方はまだ申請できません。更新申請をしたときに、3年の許可が出てからになります。
⑦公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症にかかっていないことや、慢性的な薬物中毒者でないことなどです。
就労ビザから永住者申請には身元保証人が必要
永住者の申請には身元保証人が必要です
永住者の申請をする際に必要な書類として、『身元保証書』があります。
これを1通、身元保証人に書いてもらうことになります。また、身元保証人の身分証明書として、運転免許証のコピーなども提出する必要があります。
永住者申請の身元保証人になることができるのは、次の3つのどれかに当てはまる人だけです。
①日本に住んでいる日本人
②永住者
➂特別永住者
このうちの誰かにお願いすると良いでしょう。日本人の配偶者や永住者の配偶者がいる方は、その配偶者が身元保証人になります。
そうでない方は、友達や知り合い、会社の人などにお願いする必要があります。
身元保証人について誤解が多いのは、『連帯保証人』とは違うということです。
入管法での身元保証人の責任は。。
【保証事項】
滞在費や帰国費など経済的保証、法令の遵守などの生活指導
- 法務大臣に対して保証事項を約束
- 経済的保証とあるが、賠償責任などはない
- 身元保証人に対する法的な強制力はない
- 保証事項を履行しない場合でも指導を受けるにとどまる
【身元保証人として十分な責任が果たせない場合】
それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠く
つまり、次回他の方の保証人になるのは難しいということです
【まとめると】
法的な責任というより、道義的な責任を課すものであるといえる
身元保証人を断られる理由として、保証責任について誤解があることが多いです。これをしっかり説明し、理解をしてもらう必要があります。
就労ビザから永住者申請には理由書が必要
永住者の申請には理由書が必要です
就労ビザから永住申請する場合、必要書類で『理由書』があります。
これは、永住許可を必要とする理由について、自由な形式で作成するものです。日本語以外で作成する場合は、翻訳文が必要となります。
自由な形式といっても、あまりに短すぎたり、長すぎて読みずらいものより、簡潔にまとめたものが良いでしょう。
A4用紙1~2枚くらいでまとめるのが良いです。また、横書きが読みやすい印象です。
※日本人の配偶者等や、永住者の配偶者等に該当する方は、理由書は必要ありません。
就労ビザから永住者申請の必要書類
就労ビザから永住ビザへ変更する場合の必要書類
就労ビザから永住ビザへの変更に必要な書類は次のとおりです。これをそろえて、入管に申請します。
- 永住許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 理由書(様式自由)
※日本語以外の場合、翻訳文必要 - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
(※マイナンバー省略・他は省略なし) - 職業を証明できる(a)~(c)のいずれかの資料
(a)会社等に勤務している場合 在職証明書
(b)自営業等である場合 確定申告書控えの写し 営業許可書の写し(ある場合)
(c)その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
【直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次の資料】
- 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※5年分ない場合は、発行できる最長期間 - 直近5年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方
直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等) - 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※対象期間の指定は不要 - 預貯金通帳の写し
(取引履歴が分かるweb通帳の画面のコピーも可※Excelファイルなど加工できるものはNG) - 他に所得を証明できるもの
(預貯金通帳のコピーが提出できない場合)
【申請人の①ねんきん及び②健康保険の保険料の納付状況を証明する資料】
※基礎年金番号や保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りするなど、復元できない状態にして提出
- ①直近2年間の年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 直近2年間で厚生年金などに加入している方
(a)(b)どちらか
(a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
(b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 - 直近2年間で厚生年金+国民年金加入の方
(a)(b)どちらか+(c)
(a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
(b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
(c)国民年金保険料領収証書のコピー - 直近2年間すべて国民年金加入の方
国民年金保険料領収証書のコピー
提出することが困難な場合は、理由書+ねんきん定期便又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面を提出
- ②直近2年間の健康保険料の納付状況を証明する資料
- 現在、国民健康保険以外の健康保険に加入
健康保険被保険者証のコピー - 現在国民健康保険に加入中の方
国民健康保険被保険者証のコピー - 直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方
国民健康保険料(税)納付証明書
国民健康保険料(税)領収証書のコピー(提出が困難な方は、理由書を提出)
- 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
(a)または(b)を提出
(a)健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー(※直近2年間のうち事業主である期間)
(b)社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
- 申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
(a)預貯金通帳の写し(取引履歴が分かるweb通帳の画面のコピーも可※Excelファイルなど加工できるものはNG)
(b)不動産の登記事項証明書
(c)上記(a)(b)に準ずるもの - パスポート又は在留資格証明書(提示)
- 在留カード(提示)
- 資格外活動許可書(提示)
※許可書を交付されている場合 - 身元保証書
- 身元保証人の身分を証明できる書類
(運転免許証コピーなど) - 了解書
- 日本への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
各分野において貢献があることに関する資料
contact
ご家族も一緒に永住許可申請したい方は、一度ご相談ください。
全員で申請できるかを確認させていただきます。
他にも、自分で申請する時間がない方、書類作成の手間をなくしたい方、書類がよくわからない方などのために、当事務所では書類作成や入管申請、結果受取まで代行いたします。ぜひご利用ください。
初回相談無料(1時間)
まずは、お問い合わせフォーム(24時間受付)又はお電話でご相談予約をよろしくお願い致します。こちらからご返信いたします。
・初回1時間程度 無料
・ご相談 ¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料はかかりません。事前にご予約頂いた方を優先的にご案内させていただきます。
contact
お問い合わせ
受付時間:9:00~19:00
(土日祝 対応可能)
24時間受付
(1営業日以内にご連絡いたします)
出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)